アルプス電気盛岡工場が閉鎖され、これをきっかけに高い技術力を持った社員たちが早期退職し、次々とベンチャー企業を起こした。その結果、各ベンチャーが、技術力を互いに交換し、密接に連携・取り引きしながら存続しているという希有な現象が起こった。
さらに、アイカムス・ラボのpipettyの成功によって、医療機器製造業に可能性を見て取る。リーマン・ショック後は、ダメージが少なかった医療産業に力を入れるべきだと、県も旗を振りだし、とりあえず勉強会を企画した。
しかし、片野らは「県の動きは遅すぎる」「発展性に欠ける」と判断し、独自に勉強会を立ち上げた。この「医療機器事業化研究会」にふらりと東京からやってきたのが、当時はメタロジェニクスという試薬メーカーを経営していた岩渕拓也であった(メタロジェニクスは現在も操業)。
【登場人物】
片野圭二
現在TOLIC(東北ライフサイエンス機器クラスター)の中心的人物。アルプス電気盛岡工場の操業停止をきっかけに、地元でアイカムス・ラボというベンチャー企業を立ち上げ、同種のベンチャーとの協業を図りながら、地方再生のプロジェクトに取り組んでいる。
岩渕拓也
千葉大学・亥鼻インキュベーター(中小機構)内でメタロジェニクスという試薬会社を経営していたが、片野が主催していた医療機器についての勉強会「医療機器事業化研究会」に参加したことをきっかけに、ともに盛岡で事業を起こそうと、セルスペクトという会社を立ち上げる。
フィジカル+ITデジタル=フィジタルメーカーで勝負をかける男
今回は、岩渕拓也が率いるセルスペクトを取り上げる。そしてセルスペクトこそTOLIC(東北ライフサイエンス機器クラスター)の起爆剤である。
地方の工場が閉鎖し、そこから多数のベンチャー企業が生まれ、連携しながら存続しているという事実は、確かに称賛に値する。
しかし、数字的な観点から冷酷に査定すれば、それほど目覚しいものとは言えない。片野圭二のアイカムス・ラボも上場への計画を進めてはいるが、いまだに離陸できていないというのが現状だ。
岩渕拓也は、片野圭二とはまったく異なる経営思想の持ち主である。まず、片野圭二は“ものづくり”を信じている。アルプス電気という部品メーカーにいた片野にとっては、セット商品を作ることは夢であった。
一方、岩渕拓也に「セルスペクトはメーカーなのですか」と質問すれば「メーカーです」と明言しつつ、それだけでは駄目なのだと含みを持たせた発言をする。ここに岩渕の複雑さが、かいま見える。
メーカーであることを自覚しつつ、同時に岩渕が強く意識しているのは、金融資本主義のメカニズムである。岩渕には三つの戦略がある。そのひとつは株式上場による企業規模の拡大だ。
ベンチャーから卒業し、大企業になること。しかし、「医療機器メーカー」を名乗ってマーケットに打って出るのと、フィジタル企業(フィジカル+ITデジタル)として乗り込むのとでは、将来像に雲泥の差が出る。つまり、市場はものづくりを信じていないということだ。
このことを岩渕は強く自覚しており、この点が、ものづくりにいまだロマンを感じている片野とは異なる。ちなみに、ふたりを主人公にして別々のドラマを作った場合、人気が出るのはまちがいなく片野のストーリーのほうだろう。
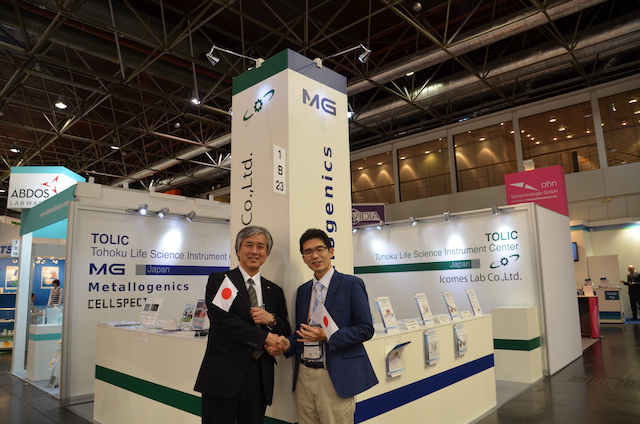 (左)アイカムス・ラボ 片野圭二 (右)セルスペクトル 岩渕拓也
(左)アイカムス・ラボ 片野圭二 (右)セルスペクトル 岩渕拓也
ものづくりに執着しつつも、目指すは株式上場
片野は自身の会社にアイカムス・ラボと命名したが、このアイは“I”、宮沢賢治が掲げた「イーハトーボ」に由来する。このように片野はどこかで、空想社会主義的な理想を夢見ている。
それに対して、岩渕はそんな遠くは見ない。岩渕が注視しているのは我々の社会が立脚している足下、金融資本主義の成長メカニズムである。
そして、時代の流れに照らしてみれば、圧倒的に正しいのは岩渕の戦略のほうだ。例えば、経済学者の野口悠紀雄は「モノづくり幻想が日本経済をダメにする」(著書名)とまで言っている。
しかし、株式上場による大規模資金調達には弊害もある。資金調達が自己目的化し、創業者利益の顕在化や、企業の知名度や信用度の向上だけのために行われる場合も多い。また、株主は貪欲にROE(Return On Equity 自己資本利益率)を求め、この期待に応えるために経営者が従業員の給与を圧縮するなどということも起こり得るし、実際にそんな例は枚挙にいとまがない。
このような現状を「株主資本主義」と呼んで告発しているのが、初期のシリコン・ヴァレーでベンチャーキャピタリストとして活躍していた原丈人である。
では、岩渕には、ものづくりに対する執着はないのかというと、現にセルスペクトはものづくりを行っている。つまりは、あるのだ。その代表がPOCT(Point Of Care Testing)の装置である。
エポックメイキングは日本ではなく、アジアから
POCTは「臨床現場即時検査」と訳されるが、字面を眺めてもピンと来ないだろう。セルスペクトの場合に限って言えば、小型の血液検査装置だと理解しておけばいい。これを使ったヘルスチェックサービスをドラッグストアの薬王堂と展開しようとしているのである。
のど飴やミネラルウォーターを買いにドラッグストアに立ち寄った人に、その場で血液項目の測定をしてもらい、数分後にはその結果を渡す。セルスペクトはこのヘルスチェックの装置を開発した医療機器メーカーである。
さらに興味深いのは、これらを病院ではなく、ドラッグストアに収め、そこで健康チェックという無料サービスを展開するという目論見である。これは、従来の医療機器メーカーにはなかった発想だ。
しかし、このアイディアを聞いた当初、確かに興味深くはあるが、ドラッグストアで簡易的に健康チェックを行う人がどのぐらいいるのかと考えると、首を傾げざるを得ない。日本は健康診断、ヘルスチェックのインフラが相当に整っている。
さらに国民皆保険制度もある。「最近どうも体調が思わしくないなぁ」と思っていた人が、ドラッグストアでふと思い立ってPOCTの被験者になるということは、あるにはあるだろう。しかし、健康に関する日本人の行動パターンを変えるほどのブームになるのだろうか、と考えると大いに疑問が残る。
ところが、店舗や各地のイベントでは、その懸念をよそに、体験しようという人の長蛇の列ができ、試験サービス中の現在も月に千人を超える利用者があるという。さらに、企業健保や自治体健康啓発イベントなどの引き合いが引きも切らないのだ。
さらにインタビューを進めるうちに、日本では、ドラッグストアの薬王堂における消費者の購買行動と健康チェックの匿名データとをリンクさせてそれを情報のパッケージとし、その情報パッケージを販売することも考えているという。
また、このインタビューの最中に岩渕が、医療機器のものづくりと物販事業については、「日本のマーケットよりもむしろ、新興国を皮切りに、アジア全域を狙う」と発言した時には、先の考えを完全に改めた。
岩渕自身も、日本ではエポックメイキングな市場開拓ができるとは考えておらず、主たるマーケットを、医療インフラが未整備な新興国に定めているのである。そのような国、例えばインドでは、POCTの販売は大きな成果をもたらすような予感がする。
中東、サウジ、UAEの大企業と組む、真の意味での“自立”を目指す
問題は、どのようにその販路を切り開くかだ。そこでセルスペクトがタッグを組んだのが、ジャミール商事である。
ジャミール商事の本社は、サウジアラビアのジェッタ、アラブ首長国連邦のドバイに本社を置くアブドゥル・ラティフ・ジャミールだ。トヨタのレクサスの中東や南インドにおける販売代理店も務める大企業である。
ジャミール社の販売網に乗せて、自社のPOCTを販売しようという計画は、かなり手堅い戦略のように思われる。株式上場、情報パッケージの販売、そして海外進出──これらが岩渕の戦略である。
インタビューの最中、岩渕はなんども「自立」という言葉を口にした。
それは、いつまでも、国や県の補助金を当てにするなという、仲間達への戒めを含意しているようであった。さらに、ベンチャーはいずれ、ベンチャーというステージから卒業しなければならない(つまり上場、岩渕にとってはある種の自立)と岩渕は信じている。
岩渕拓也は1978年生まれ、いわゆるロスジェネ世代であり、大企業の正社員としてじっくり技術と向き合ってこられた片野たちとはまったくちがう不安定で地味なキャリアを経て現在に至っている。
そう考えると、岩渕が、片野と出会い、意気投合し(片野圭二はセルスペクトの取締役でもある)、ともにTOLICを立ち上げたということは興味深い。一見、ドライでシニカルに見える岩渕だが、「独り勝ち」以上のものを夢見ている気がするからだ。
(続く)
【連載】東北再生
第1話 新年の盛岡。激震が走った工場撤退の一報
第2話 「岩手に起業家はいるのか」・・・疑念からはじまった県のベンチャー支援
第3話 はじまった盛岡、ベンチャー狂騒曲
第4話 集う実力派エンジニア。始動した第一号ベンチャー
第5話 4250万円の開発資金を手にした時に見えた、女神の姿
第6話 進まぬベンチャー支援。盛岡に光を!
第7話 産官連携の新たな形。投資の理由は、片野圭二という男の可能性
第8話 夢、破れた男。そして再起
第9話 夢破れた至高の技術で、男は再び勝負する
第10話 盛岡に現れた、新たな雄。東北を動かす異端の登場
第11話 高校生とドイツへ。そこで明らかになった日本、そして盛岡の立ち位置
最終話 盛岡で起きた、必然という名の奇跡
文・榎本憲男(えのもとのりお)
小説家 『エアー2.0』で大藪春彦賞候補。ロックとオーディオ好きな刑事を主人公にした『真行寺弘道シリーズ』で新しい警察小説の可能性を切り拓いたと注目を浴びる。最新刊は『エージェント 巡査長 真行寺弘道』。